2011-05-12
_ TCO マラソン Round 1 終了
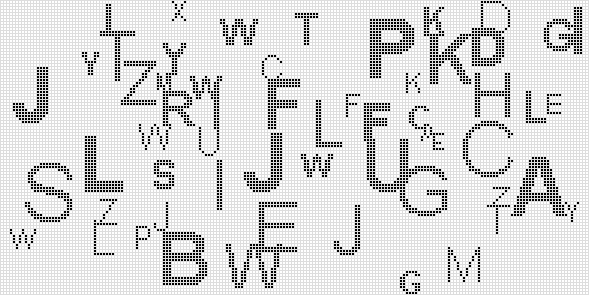
こういう画像があるので、 頑張ってどこが黒い点でどこが白い点かを推測しなさい、という問題。 プログラムは見たい行の答えを聞くことができて、 聞いた行は当然得点にならないので、 なるべく見る行数を少なくしつつたくさん正しい情報を推測できると良い。 フォントデータは与えられてるから、そのへんから推測する感じ。
僕は 4.5 行に一行ずつ開いてみて そこからそれっぽいアルファベットを適当に推測するとかそんな感じでやった。
当たり前だけど、 アルファベット一つに確定させる感じでやってたのはとりあえず良くなかったぽい。 @colun さんの twitter を読むに、 複数のアルファベットを使える可能性がある場合は、 ピクセルごとにそこが黒くなる確率を調べて そこが 50% 越えると黒とするとかが良かったようだ。 当たり前だ…
あと @colun さんがやったという、 前の行の情報から次開くべき行を確率的に調べる、 みたいなのはやった方がいいんだろうなーとは思ったけど、 どのくらい効くもんかなーというのが予想できなかったのと、 まあどうせ round 1 は通過できるだろうよ…と めんどくさくなって全然手をつけなかった。
いい問題だったと思う。 ただ解答のバリエーションが出にくい感じではあったかなぁ。 あんまりマジメにやってないのにそういうこと言うのも申し訳ない感じだけど。
まぁ round 2 行けると思うんで次から頑張ろうかと思う。 ていうか頑張らんと round 3 行けないよね…
(23:27)
_ Gimite [> (funciton(){ > // ... > })(); そこでCoffee Script、なん..]